なぜ組織の定義が重要なのか
私たちは日々、さまざまな「組織」に所属して活動しています。
会社、行政、NPO、プロジェクトチーム──どれも組織ですが、「組織とは何か」とあらためて問われると明確に答えるのは難しいかもしれません。
経営学の古典的理論において、チェスター・バーナードは『経営者の役割』(1938年)において、組織の定義を「共通の目的・貢献意欲・コミュニケーション」の3要素で説明しました。
この3要素は単に理論的な枠組みにとどまらず、現代の組織マネジメントやチームづくりにも活かすことができます。
本記事ではそれぞれの要素を実務にも落とし込める形で再解釈し、組織の本質について深掘りします。
組織の3要素とは
バーナードが提唱した組織の成立要件は以下の3つです:
共通の目的(Common Purpose)
貢献意欲(Willingness to Contribute)
コミュニケーション(Communication)
これらが同時に満たされてはじめて、人間の集合は「組織」として機能します。
共通の目的:方向性の一致
組織には構成員が共有し、目指すべき「目的」が必要です。
これは単なるスローガンではなく組織活動の判断基準となる軸です。
たとえば製造業であれば「高品質な製品を安定供給する」学校であれば「生徒の成長を支援する」など、具体的な目標設定がなされている必要があります。
この目的が曖昧だったり構成員によって認識が異なると、行動がバラバラになり組織は機能不全に陥ります。
したがって、ビジョンや経営理念の策定と共有は組織構築の基礎となる取り組みです。
貢献意欲:自発的な参加意志
共通の目的が定まっていても、それに対して「自分が貢献しよう」とする意欲がなければ組織は動きません。
ここでの「貢献意欲」は報酬だけで説明されるものではなく、理念や使命への共感、自己成長の機会、職場環境、評価制度など複合的な要素により左右されます。
バーナードは人は一定の条件が満たされれば組織に協力するが、それを維持するには組織が個人のニーズに応えなければならないと述べています。
現代で言えば、エンゲージメントやパーパス経営とも通じる概念といえるでしょう。
コミュニケーション:組織をつなぐインフラ
組織内部で意思疎通が図れない状態では共通の目的も貢献意欲も維持できません。
コミュニケーションは組織を機能させるための“見えないインフラ”です。
単に情報を一方向に伝えるだけでは不十分で、双方向性と透明性が求められます。
現代においてはテクノロジーの発達により手段は多様化しましたが、信頼を基盤とする“関係性としてのコミュニケーション”は依然として不可欠です。
要素が欠けるとどうなるか
| 欠けている要素 | 組織に生じる問題 |
|---|---|
| 共通の目的 | 方向性のブレ、戦略不在、部門間での軋轢 |
| 貢献意欲 | モチベーションの低下、離職の増加 |
| コミュニケーション | 心理的安全性の低下、誤解やミス |
どれか一つでも欠ければ、組織の安定性・生産性は損なわれます。
組織の健全性を保つための実践
バーナードの理論を現代の組織運営に適用するには、次のような取り組みが有効です。
| 要素 | 実践的アプローチ |
|---|---|
| 共通の目的 | 経営理念・ビジョンの策定、共有ワークショップの実施 |
| 貢献意欲 | 権限移譲、フィードバック文化の醸成、適切な報酬制度 |
| コミュニケーション | 定期的な1on1、部門横断的な対話の機会、情報のオープン化 |
特に中小企業では、経営者の考えがそのまま組織文化に反映されやすいため、経営理念の明確化は重要です。
終わりに──組織の本質は“構造”ではなく“関係性”
組織というと階層構造や制度ばかりに目が行きがちですが、本質は人間関係です。
共通の目的があり、それに向かって貢献したいという意欲があり、それを支える適切なコミュニケーションがある。
──この3つが機能してこそ、組織は持続的に成果を生み出す共同体になります。
LING SMEC Partnersでは、企業が本質的な組織づくりを実現するお手伝いをしています。
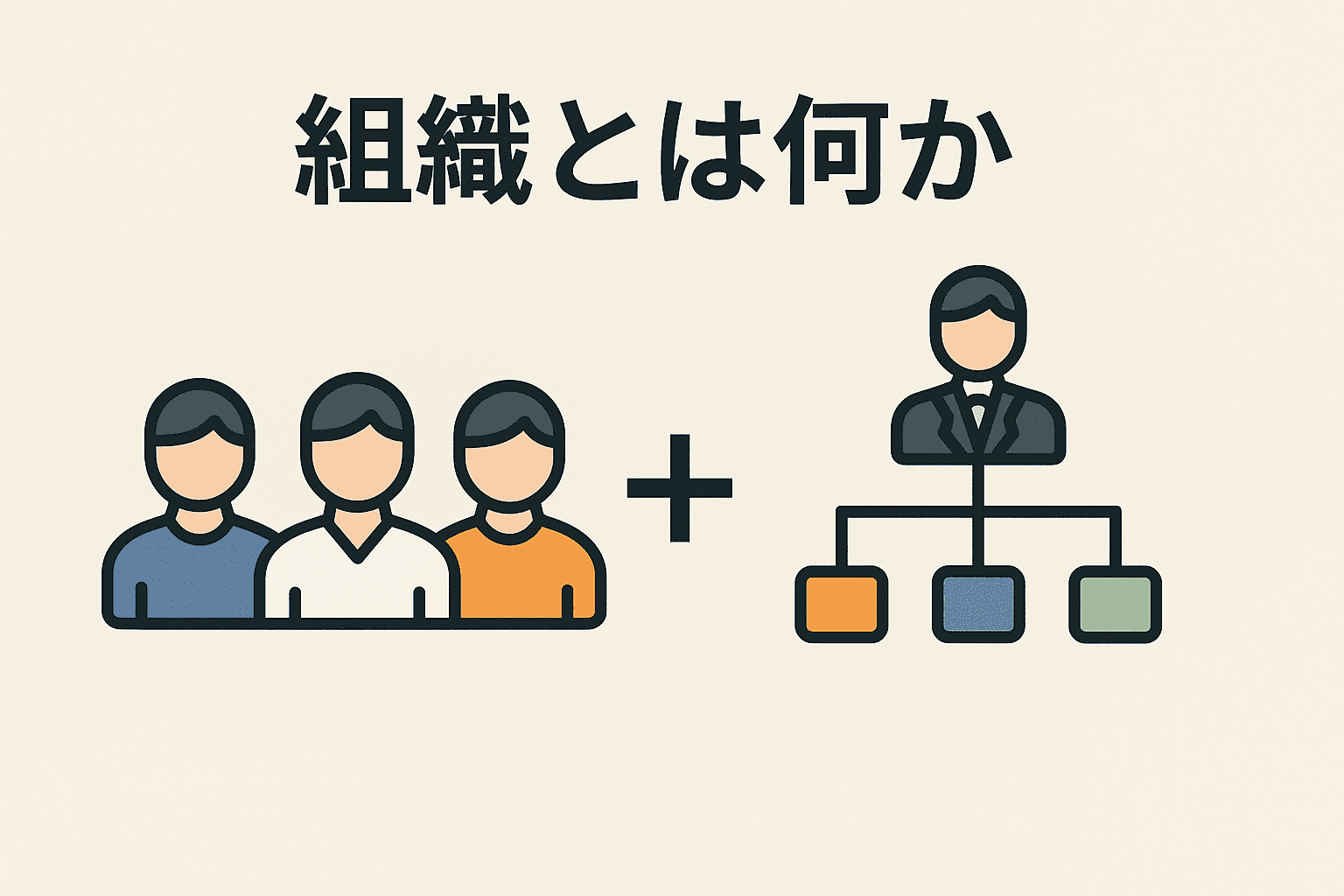
コメント